内容とプロフィール
話の主なトピック
映画監督としてのこれまで歩み、新作『海辺の彼女たち』の企 画の成り立ち、ベトナムのオーディションなど撮影の準備、 ベトナムそしてミャンマーへの思い、スペイン・サンセバスチャン国際映画祭の渡航話、コロナ禍での上映の様子
プロフィール
1988年生、大阪府出身。ビジュアルアーツ専門学校大阪で 映像制作を学ぶ。
日本に住むあるミャンマー人家族の物語を描いた長編初監督作『僕の帰る場所』(18/日本=ミャンマー) が、第30回東京国際映画祭「アジアの未来」部門2冠など受賞を 重ね、33の国際映画祭で上映される。
長編二本目となる『海辺の彼女たち』(20/日本=ベトナム) が、国際的な登竜門として知られる第68回サンセバスチャン 国際映画祭の新人監督部門に選出された。
現在、アジアを中心に劇映画やドキュメンタリーなどの制作活動を行っている。
なお、この映画については、第3回「楽平家オンラインサロン」でも取り上げました。
映画監督としてのこれまで歩み、新作『海辺の彼女たち』の企 画の成り立ち、ベトナムのオーディションなど撮影の準備、 ベトナムそしてミャンマーへの思い、スペイン・サンセバスチャン国際映画祭の渡航話、コロナ禍での上映の様子
- 司会進行の栗原佳美がインタビューをしていきます。
プロフィール
1988年生、大阪府出身。ビジュアルアーツ専門学校大阪で 映像制作を学ぶ。
日本に住むあるミャンマー人家族の物語を描いた長編初監督作『僕の帰る場所』(18/日本=ミャンマー) が、第30回東京国際映画祭「アジアの未来」部門2冠など受賞を 重ね、33の国際映画祭で上映される。
長編二本目となる『海辺の彼女たち』(20/日本=ベトナム) が、国際的な登竜門として知られる第68回サンセバスチャン 国際映画祭の新人監督部門に選出された。
現在、アジアを中心に劇映画やドキュメンタリーなどの制作活動を行っている。
- ベトナム人技能実習生に焦点を当てた長編第2作『海辺の彼女たち』は、東京中野の『ポレポレ東中野』で、5月1日から7日まで 公開中です。また、映画の舞台となった青森の、『青森松竹アムゼ』でも、5月1日から6日まで公開中です。さらに、大阪では、『大阪シネ・ヌーヴォ』で、5月8日(土)から28日(金)まで上映されます。詳細はこちら。
- 日本で暮らすミャンマー人の家族を描く長編第1昨『僕の帰る場所』は、「ミャンマー支援チャリティー」として、5月1日から7日まで公開中です。詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、この映画については、第3回「楽平家オンラインサロン」でも取り上げました。
【楽平家オンラインサロン 第9回報告】
今回は、長編二作目である『海辺の彼女たち』が現在公開中の藤元明緒監督をお迎えしました。藤元監督は、長編処女作となる前作『僕の帰る場所』(2017)で日本に暮らすミャンマー人一家を描き、今作では技能実習生として来日したベトナム人女性を描いています。どちらも日本で暮らす外国の方々がテーマとなっています。前半は栗原佳美さんによるインタビュー、後半は参加者からの質問という二部構成となり、企画を立てるまでのお話、また監督の映画の特徴であるドキュメンタリーのような映像作りのお話、さらには監督の映画に対する熱い思いなど、さまざまな貴重なお話を伺うことができました。今回も70名以上が参加し、予定の1時間半を過ぎてもまだまだ議論が続く大盛況となりました。
【前半】栗原佳美さんによる藤元明緒監督へのインタビュー
――まずは、藤元監督がどのようにして映画監督を志すようになったのか、また長編一作目である『僕の帰る場所』の製作までの経緯についてお話しいただけますか。
元々はテレビの編集やミュージックフェスのカメラマンに憧れて、大学卒業後に大阪のビジュアルアーツ専門学校に入学しました。それまでの映画体験は人並み程度でしたが、専門学校時代にミニシアターでアート映画に触れ、映画は面白い/面白くないだけでなく、映画から何かを人生を学ぶことができ、また登場人物に対して全然違う国の人にもかかわらず、これは僕の物語なんじゃないかと自分事になる瞬間があることを知りました。自分もこういう映画が作りたいと思いから映画にシフトしていきました。
専門学校卒業後、テレビ業界と違って映画業界は就職がありませんでした。以前のように映画撮影所で監督のアシスタントから監督になっていくシステムはなくなっており、みんなフリーランスでやっていたので自分もそれにならいました。卒業制作では短編を撮り、それがありがたいことにアメリカで上映されたのですが、同時に面白くないなどの批判もたくさん受けました。その悔しさをバネに、卒業後は長編映画を作ろうと思い、それが『僕の帰る場所』になりました。
『僕の帰る場所』は、振り返ると縁に恵まれていたと思います。ミャンマーに行ったことすらありませんでしたが、準備を続ける中でたくさんの人と出会いました。元々、この映画に関しては、日本の映画館で公開されるとは思っていませんでした。日本では有名な原作や俳優が出ていないと興行的には難しいので、ミャンマーの一般家庭の映画など誰も見ないだろうと。しかし、ふたを開けると全国の人に見てもらえて、それで2作目も作ることになりました。正直なところ、1本でやめようと思っていたんです。給料をもらっているわけでもなく、仕事の合間にやっているので。ただ、一作目で自分がかつてアート映画で得た体験を自分以外の人が感じてくれていることがわかり、自分はこのために映画をやっているのだと再確認しました。
専門学校卒業後、テレビ業界と違って映画業界は就職がありませんでした。以前のように映画撮影所で監督のアシスタントから監督になっていくシステムはなくなっており、みんなフリーランスでやっていたので自分もそれにならいました。卒業制作では短編を撮り、それがありがたいことにアメリカで上映されたのですが、同時に面白くないなどの批判もたくさん受けました。その悔しさをバネに、卒業後は長編映画を作ろうと思い、それが『僕の帰る場所』になりました。
『僕の帰る場所』は、振り返ると縁に恵まれていたと思います。ミャンマーに行ったことすらありませんでしたが、準備を続ける中でたくさんの人と出会いました。元々、この映画に関しては、日本の映画館で公開されるとは思っていませんでした。日本では有名な原作や俳優が出ていないと興行的には難しいので、ミャンマーの一般家庭の映画など誰も見ないだろうと。しかし、ふたを開けると全国の人に見てもらえて、それで2作目も作ることになりました。正直なところ、1本でやめようと思っていたんです。給料をもらっているわけでもなく、仕事の合間にやっているので。ただ、一作目で自分がかつてアート映画で得た体験を自分以外の人が感じてくれていることがわかり、自分はこのために映画をやっているのだと再確認しました。
――今回は国も違いますし、調査なども大変だったのではないでしょうか?そのあたりも含めて、二作目の製作の経緯についてお話しいただけますか。

インタビュアーの栗原佳美さん
2作目はベトナムとの合作です。ベトナム人を扱っていますが、ベトナム人でなくても見られる映画になっています。これは自分が外国の人と結婚したという経験が大きいです。ミャンマー人の妻は留学生として来日し、彼女から日本での暮らしの大変さを聞いていました。こうした自分の経験から、2作目も外国籍の方の労働者を扱った映画になりました。
元々、国や地域は決めておらず、先に物語がありました。アイデアは、2016年に技能実習生の方とメールでやりとりをしていたことに始まります。実習先で不当な扱いを受け、逃げたいという相談でしたが、結局助けられず、実習先から逃げて行方不明になってしまいました。そうするとオーバーステイになるだろうし、職につけたとしても非正規でしょう。当時も技能実習生制度の問題はニュースになっていましたが、逃げたあとのことは報道されません。僕はむしろ、逃亡後の彼らの人生に興味が湧いて、脚本づくりを始めました。『海辺の彼女たち』の冒頭は、実習生が実習先を逃げるところから始まっています。
役者についてですが、前回は知人の紹介ベースで出会ったのですが、今回はベトナムで100人くらいオーディションして選びました。実際の女優というより、その人の人生が脚本とマッチしているかどうかを重視しました。『海辺の彼女たち』の出演女性の一人は、お姉さんが台湾に出稼ぎに行って10年経つらしく、その間まったく会えていないと言っていました。また映画に出ることは姉を演じることになることになるかもしれないとも。前回のカウン君たちも彼ら自身が日本で生まれ育ったというところが大きかったです。
元々、国や地域は決めておらず、先に物語がありました。アイデアは、2016年に技能実習生の方とメールでやりとりをしていたことに始まります。実習先で不当な扱いを受け、逃げたいという相談でしたが、結局助けられず、実習先から逃げて行方不明になってしまいました。そうするとオーバーステイになるだろうし、職につけたとしても非正規でしょう。当時も技能実習生制度の問題はニュースになっていましたが、逃げたあとのことは報道されません。僕はむしろ、逃亡後の彼らの人生に興味が湧いて、脚本づくりを始めました。『海辺の彼女たち』の冒頭は、実習生が実習先を逃げるところから始まっています。
役者についてですが、前回は知人の紹介ベースで出会ったのですが、今回はベトナムで100人くらいオーディションして選びました。実際の女優というより、その人の人生が脚本とマッチしているかどうかを重視しました。『海辺の彼女たち』の出演女性の一人は、お姉さんが台湾に出稼ぎに行って10年経つらしく、その間まったく会えていないと言っていました。また映画に出ることは姉を演じることになることになるかもしれないとも。前回のカウン君たちも彼ら自身が日本で生まれ育ったというところが大きかったです。
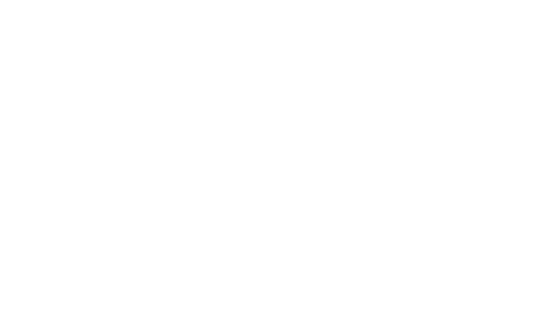
藤元明緒監督
【後半】参加者からの質問コーナー
Q:採算性についてはどのように考えていますか。人が入らなければ赤字も覚悟ということでしょうか。
A:今回は合作でベトナムの製作会社と日本の制作者が資金を出し合っています。ベトナム公開もできるようなチームで製作しています。日本側は前作のメンバーとまったく同じメンバーで、これは映画製作では珍しいことです。監督が決まり、作品に応じてカメラマン、音楽などを外部に発注していくのが普通のやり方ですが、僕らの場合は、僕やプロデューサー、そしてカメラマンがどういう映画を作りたいかという話し合いから始まっています。
また僕らの映画はドキュメンタリー調ですので、こういった映画を作るには同じチームで作品作りを重ねたほうがよいと考えています。
赤字の心配については、まず、僕とプロデューサーを除いて人件費は支払って集まってもらっています。ただ僕ら中枢の人間は、人が入らなければ赤字です。今は緊急事態宣言で席数半減で上映していますが、製作サイドからすると延期にしてほしいというのが正直なところです。そうでないと費用が回収できない。しかし休業要請の協力金は1日わずか2万円なので、映画館側としては開けないといけない状況で。これまでお世話になってきた映画館ばかりですので、席数半減で上映してもらっています。多くの人に見ていただければ文字通り助かります(笑)。
また僕らの映画はドキュメンタリー調ですので、こういった映画を作るには同じチームで作品作りを重ねたほうがよいと考えています。
赤字の心配については、まず、僕とプロデューサーを除いて人件費は支払って集まってもらっています。ただ僕ら中枢の人間は、人が入らなければ赤字です。今は緊急事態宣言で席数半減で上映していますが、製作サイドからすると延期にしてほしいというのが正直なところです。そうでないと費用が回収できない。しかし休業要請の協力金は1日わずか2万円なので、映画館側としては開けないといけない状況で。これまでお世話になってきた映画館ばかりですので、席数半減で上映してもらっています。多くの人に見ていただければ文字通り助かります(笑)。
Q:藤元監督の映画はドキュメンタリー調の社会派映画と言われることが多いですが、それはマーケットを意識しての戦略的なものなのでしょうか。また昨今のソーシャルメディアの発達の中で、メディアとしての映画が今後どうなっていくと予想されますか。
A:僕らは映画だけの世界を打ち出しすぎないことを大事にしています。「これって映画だけの世界だよね」と言われたらおしまいだと思っています。90分で描かれていること以上のことを持ち帰ってもらうのが目標です。実際に社会で起きていることと映画で描かれていることが連続するというか、「こういうこと僕たちの世界であるよね」という自分たちの現実とリンクするような映画作りを目指しています。
こうした映画が日本でももっと出てくるでしょう。ファンタジーすぎると映画で描かれる世界と自分が生きている世界がどんどん遠くなってしまい、それはエンタメとしては正解かもしれませんが、自分としては、映画は今後さらに現実を知るためのメディアになっていくのではと考えています。これまではそれはドキュメンタリーの分野が担っていましたが、今後フィクション映画にもそういった映画が増えてくると予想しています。
戦略性は度外視して作っています。観た人がどう思うかが一番の基準です。こうしたら売れるだろうというのは持ち込まないようにしています。その理屈を持ち込むと、キムタクを起用するとかそういう話になり、また自分がやりたいテーマともずれてしまいます。そういうスタイルが好きではないのでやっていません。ただそうすると動員数の問題になりますが、地道にやっていけばこういうスタイルが定着すると信じています。
こうした映画が日本でももっと出てくるでしょう。ファンタジーすぎると映画で描かれる世界と自分が生きている世界がどんどん遠くなってしまい、それはエンタメとしては正解かもしれませんが、自分としては、映画は今後さらに現実を知るためのメディアになっていくのではと考えています。これまではそれはドキュメンタリーの分野が担っていましたが、今後フィクション映画にもそういった映画が増えてくると予想しています。
戦略性は度外視して作っています。観た人がどう思うかが一番の基準です。こうしたら売れるだろうというのは持ち込まないようにしています。その理屈を持ち込むと、キムタクを起用するとかそういう話になり、また自分がやりたいテーマともずれてしまいます。そういうスタイルが好きではないのでやっていません。ただそうすると動員数の問題になりますが、地道にやっていけばこういうスタイルが定着すると信じています。
Q:映画を撮るというのは自分にとっては別世界で想像がつかないが、小説を映画化する場合は、小説を書きおろしたり、ナレーション風にしたりというのを聞いたことがある。藤元監督の場合は小説からではなくドキュメンタリー風ということで、どういうかたちで書き下ろしていって、映画を撮り始めるのか教えてほしいです。また現在のミャンマーの現状も映画化の予定はありますか。
A:映画を撮るモチベーションがどこから来るかというと、一番は自分の身近に感じたことです。それは前回、今回も同じです。社会的な問題に対して、今こういう問題があるから、こういうことを言いたいというのが先に来ているわけではありません。よく社会派映画と言われるのですが、それはあとから追いついていることであって、あくまでも自分の身近なことをみんなに共有したいという思いで映画を作っています。
自分がどういう監督人生を歩むかわかりませんが、今ミャンマーで起きていることは無視できないでしょう。間違いなく自分の作品の一つにならないといけない、描かないといけないという使命感があります。実は先月ごろ、みんなにカメラを持ってもらって、リモートで映画を作れないか考えたのですが、今となってはやらなくてよかったと思っています。カメラを取り出したら逮捕されてしまう状況ですので。なので、今はどういうアプローチがあるか悩んでいるところです。映画は「今」を解決する力はありませんが、このことを未来への手紙として映画に残さないといけないと思っています。
自分がどういう監督人生を歩むかわかりませんが、今ミャンマーで起きていることは無視できないでしょう。間違いなく自分の作品の一つにならないといけない、描かないといけないという使命感があります。実は先月ごろ、みんなにカメラを持ってもらって、リモートで映画を作れないか考えたのですが、今となってはやらなくてよかったと思っています。カメラを取り出したら逮捕されてしまう状況ですので。なので、今はどういうアプローチがあるか悩んでいるところです。映画は「今」を解決する力はありませんが、このことを未来への手紙として映画に残さないといけないと思っています。
Q:『海辺の彼女たち』で気になったのが、三人の女の子が働く工場に日本人がいるはずなのに、顔が出てこず、声ばかりという点です。作品全体をとおしても日本人が人格として出てきませんが、日本人の描き方をどのように工夫されたのか教えていただきたいです。
A:この映画は95%がベトナム語の映画で、日本語はほとんど出てきません。日本人側をキャラクターとして深く描いていないのは、彼女たち側自身がそこまで日本人に対して歩み寄っていないということを表しています。この映画では彼女たちから見た世界だけを切り取ろうと思っていました。日本人が映っていない理由は、彼女たちがそこにコミットしたくないという感情とリンクするようにした結果です。
Q:前作、今作ともにミャンマーやベトナムなど現地では上映されたのか、また今後上映される予定があるのかを教えてください。また上映されたのであればその時の反応を教えてください。実習生の送り出し先の国がどのように見るのかも気になります。
A:前作は現地の映画祭(インディーズ)と、国際交流基金の日本映画祭で上映しました。反応ですが、面白いことに、日本で上映してもミャンマー、ヨーロッパやアメリカで上映しても、みんなほとんど同じ感想でした。これが映画にとって良いことか悪いことかは置いておきますが、ミャンマー人だけど自分を日本人だと思っている少年の話で、少年の悲しい気持ち、成長していく気持ちについて共感してくれたようです。言語が違っても共感できるんだと改めて思いました。
ベトナムでの公開は調整中です。東京国際映画祭では、実習先から逃げた方やコロナでクビになった方など、シェルターで保護されている方を無料招待して見てもらいました。希望を持って送り出す側のベトナムの人々が今作をどう観るのかは気になっています。
ベトナムでの公開は調整中です。東京国際映画祭では、実習先から逃げた方やコロナでクビになった方など、シェルターで保護されている方を無料招待して見てもらいました。希望を持って送り出す側のベトナムの人々が今作をどう観るのかは気になっています。
Q:映画の魅力というのは共感力というのが最大の武器だと思います。①現在のミャンマーの状況や名古屋の入管の話など問題がいろいろ起きていますが、それら外部の動きと連携はありますか。②コロナ禍やクーデターなどの危機的状況では文化が死んでしまうという話が出ていますが、今はSave the Cinemaなどの活動があります。そこには携わっていらっしゃるのか、またどういう気持ちでそれを見ているのか教えてください。③これから表現してみたいと思っていることについて教えてください。
A:①ですが、善し悪しを別にして、なるべく連携をしないというところに映画の魅力があると思っています。映画から何かを受けとった人が次にとるアクションを信じています。チャリティー上映などをすると、個人として何ができるかを聞かれることが多いのですが、僕は結論としては寄付だと思っています。たとえば技能実習生を保護するシェルターも寄付を募っていて、僕もそういう情報は個人的に発信しています。
②文化が死んでしまうということについてはリアルに危機感を持っています。Save the Cinemaという運動が去年から始まっていますが、一番健康的なSave the Cinemaのやり方は、多くの方を映画館に呼ぶことだと思っています。映画館で「映画は面白い」という体験をしてもらい、それを広めていきたい。
③これから表現したいこととしては、僕は一度も日本人主演の映画を作ったことがないので、日本の方からの目をとおした外国籍の人との距離感というのを描いてみたいです。あと、さきほど話に出できたミャンマーの情勢に関する作品です。それと以前、いつものスタッフでインパール作戦の舞台となったチン州を一週間旅して『白骨街道』(2020)という16分の短編映画を製作したのですが、この題材を日本人側ではなく現地側の視点で掘り下げて長編映画を作りたいと思っています。
②文化が死んでしまうということについてはリアルに危機感を持っています。Save the Cinemaという運動が去年から始まっていますが、一番健康的なSave the Cinemaのやり方は、多くの方を映画館に呼ぶことだと思っています。映画館で「映画は面白い」という体験をしてもらい、それを広めていきたい。
③これから表現したいこととしては、僕は一度も日本人主演の映画を作ったことがないので、日本の方からの目をとおした外国籍の人との距離感というのを描いてみたいです。あと、さきほど話に出できたミャンマーの情勢に関する作品です。それと以前、いつものスタッフでインパール作戦の舞台となったチン州を一週間旅して『白骨街道』(2020)という16分の短編映画を製作したのですが、この題材を日本人側ではなく現地側の視点で掘り下げて長編映画を作りたいと思っています。
Q:前作『僕の帰る場所』に非常に感銘を受けました。私は無国籍の人の研究をしていて、私自身も30年間無国籍でした。『海辺の彼女たち』は技能実習生の話ということですが、私も、実習先から逃亡した女性から生まれてくる子供が無国籍状態になっていると聞いたことがあります。今後はそのような女性たちから生まれてくる子供たち含め、日本人の視点から日本で生まれた「外国人に見える子供たち」を描いていただく可能性もあるのかなと。
A:オーバーステイ状態になっている赤ん坊を預かる施設を取材しようと思ったことがあります。無国籍の方にはいままで2人しか会っていませんが、僕も非常に関心があるテーマです。僕がお会いしたのは大学卒業したら帰らないといけないという方で、あきらかに制度からこぼれている方です。無国籍の方を映画のテーマにするには、自分の知識がまだ足りませんが、関心があるところです。子供たちは自分でハンドリングできず、何かの都合でしか生きられません。これは最初の卒業制作から新作まで共通するテーマで、引き続き追いかけていきたいです。
Q:今日の藤元さんのお話のなかで、ドキュメンタリーではなくあえてドラマとして映画を作るところが私は面白いなと思いました。現地の方に来てもらって映画を作るということですが、そうすると当初の自分のシナリオに沿わないところやズレなどが出てくるんじゃないかなと思いました。ドキュメンタリーは撮ったものを切っていき、そのなかで最終的に筋書きをつくっていきます。自分の感性から出発して、でも社会とつながりながら映画を撮っていくときに、どこかにズレが出てきたりとか、調整したりするのかなと思い、その点がすごく面白いなと思いました。
A:僕が脚本で書いたこととどこがズレているかというと、これはドキュメンタリーとの違いにもなるんですが、役者が演じているというところです。僕が書いた物語を、あくまでも僕と違う誰かが、解釈して咀嚼して、演じ直しています。僕の思想が元々あるとしても、それが役者に渡って、役者が表現している、それを僕らが撮らせてもらっていると思っています。こういうサイクルがあるので、そこのズレ(監督の思想と役者の解釈)がフィクション映画の本当の魅力ですね。役者が芝居することによって新たな広がりが生まれると思うんですね。それに出会うことが僕にとっては喜びです。
Q:監督の考えと役者のズレもあると思いますが、さらに監督の考えと観た人とのあいだにもズレがあると思います。さきほど社会派と呼ばれることへの違和感について触れられていましたが、見る人によっては政治的メッセージを持った映画に見え、また別の人には単純にアート映画に見えると思います。その辺は作る側としては、監督の考えと観客の考えは切り分けているのでしょうか。
A:基本的に僕らの意志としては作る段階では切り分けています。社会的なメッセージを作る段階から持ち込んでしまうと、僕が役者さんに自分のメッセージを代弁してほしいという演出になってしまうんですね。せっかく一人の役者という人間なのに、僕のメッセージの媒介になってしまうと、どうしてもリアルな芝居が難しい。それよりはその人がその場で生きていて、言いたい台詞をディスカッションしながら拾っていくということをしています。上映になると別でして、映画を観た人のどのような受け止め方も僕はうれしいです。批判も含めてウエルカムです。
この他、上述の短編作品『白骨街道』についても参加者から今後の上映の可能性についての質問や、さらにインパール作戦についても情報が寄せられました。
すなわち、参加者からはインパール作戦の生き残りである加茂徳治さんのお名前が出ました(この方は、加茂さんからベトナム語を教わったそうです)。加茂さんの所属する仙台第二師団はガダルカナルからさらにインパールへ、その後フランス支配下のカンボジアには武装解除の後に丸腰で入ったそうです。その後日本軍は1945年3月9日にクーデターを起こし、フランスの植民地機構を解体させます(仏印武力処理)。加茂さんはその後も帰国せずにベトナムに残留し、独立戦争に参加したそうです。当時こうした残留日本兵が数百人はいたという貴重なお話でした。ちなみに加茂徳治さんは『クァンガイ陸軍士官学校―ベトナムの戦士を育み共に闘った9年間』(暁印書館、2008年)という回想録を書かれています。
今回は研究者の方々も何人か参加されており、それぞれの専門の観点からのコメントを含む質問も伺うことができました。
(記事執筆:山本文子)<無断転載ご遠慮ください>
すなわち、参加者からはインパール作戦の生き残りである加茂徳治さんのお名前が出ました(この方は、加茂さんからベトナム語を教わったそうです)。加茂さんの所属する仙台第二師団はガダルカナルからさらにインパールへ、その後フランス支配下のカンボジアには武装解除の後に丸腰で入ったそうです。その後日本軍は1945年3月9日にクーデターを起こし、フランスの植民地機構を解体させます(仏印武力処理)。加茂さんはその後も帰国せずにベトナムに残留し、独立戦争に参加したそうです。当時こうした残留日本兵が数百人はいたという貴重なお話でした。ちなみに加茂徳治さんは『クァンガイ陸軍士官学校―ベトナムの戦士を育み共に闘った9年間』(暁印書館、2008年)という回想録を書かれています。
今回は研究者の方々も何人か参加されており、それぞれの専門の観点からのコメントを含む質問も伺うことができました。
(記事執筆:山本文子)<無断転載ご遠慮ください>
アンドモア
●『海辺の彼女たち』公式サイト
https://umikano.com/
●映画の秘蔵資料や制作スタッフと交流できるオンラインコミュニ ティ(非公開Facebookグループ)
https://umikano-ouen.studio.site/
●『僕の帰る場所』 チャリティ上映情報
https://bokukaecharity.studio.site/
●藤元明緒監督SNS
Twitter:@akio_fujimoto
Facebook: https://www.facebook.com/akio.fujimoto1031
●藤元明緒監督インタビュー
https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0018/topic034.html?fbcl%20id=IwAR2tu9YJWfN%205OLxbziJ74UwVk_A_hgD-_FvdPutKU%20ojJs7cwpYNqAGaaxdc
●短編『白骨街道』について;
エクスンの公式HPより
http://exnkk.com/
Youtubeの予告編
https://www.youtube.com/watch?v=oLngm20g-3c
https://umikano.com/
●映画の秘蔵資料や制作スタッフと交流できるオンラインコミュニ ティ(非公開Facebookグループ)
https://umikano-ouen.studio.site/
●『僕の帰る場所』 チャリティ上映情報
https://bokukaecharity.studio.site/
●藤元明緒監督SNS
Twitter:@akio_fujimoto
Facebook: https://www.facebook.com/akio.fujimoto1031
●藤元明緒監督インタビュー
https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0018/topic034.html?fbcl%20id=IwAR2tu9YJWfN%205OLxbziJ74UwVk_A_hgD-_FvdPutKU%20ojJs7cwpYNqAGaaxdc
●短編『白骨街道』について;
エクスンの公式HPより
http://exnkk.com/
Youtubeの予告編
https://www.youtube.com/watch?v=oLngm20g-3c
次回からの「楽平家オンラインサロン」
7月の予定は、オーストラリアから、ミャンマー文学とミャンマーの国民食モヒンガーについて、オーストラリアから高橋ゆりさんのお話しです。いつも通り、第2水曜日14日の午後8時から9時半まで(日本時間)です。
8月は11日に、135以上のミャンマー民族の布でバッグをつくる、ファブリックブランド『モリンガ』を立ち上げた、 二人の女性が、それぞれ、ミャンマーのヤンゴンと東京からお話をされます。
9月は8日に、ミャンマーの少数民族、シャンの社会や文化を長く研究されてきている、高谷紀夫さんがお話しされる予定です。
8月は11日に、135以上のミャンマー民族の布でバッグをつくる、ファブリックブランド『モリンガ』を立ち上げた、 二人の女性が、それぞれ、ミャンマーのヤンゴンと東京からお話をされます。
9月は8日に、ミャンマーの少数民族、シャンの社会や文化を長く研究されてきている、高谷紀夫さんがお話しされる予定です。
Laphetye

