『楽平家オンラインサロン』
歴史の基層から現代の旧遊牧民芸能へ:
遊牧世界と定住世界の接触地帯としてのウズベキスタン
2025年1月15日(水)
20:00〜
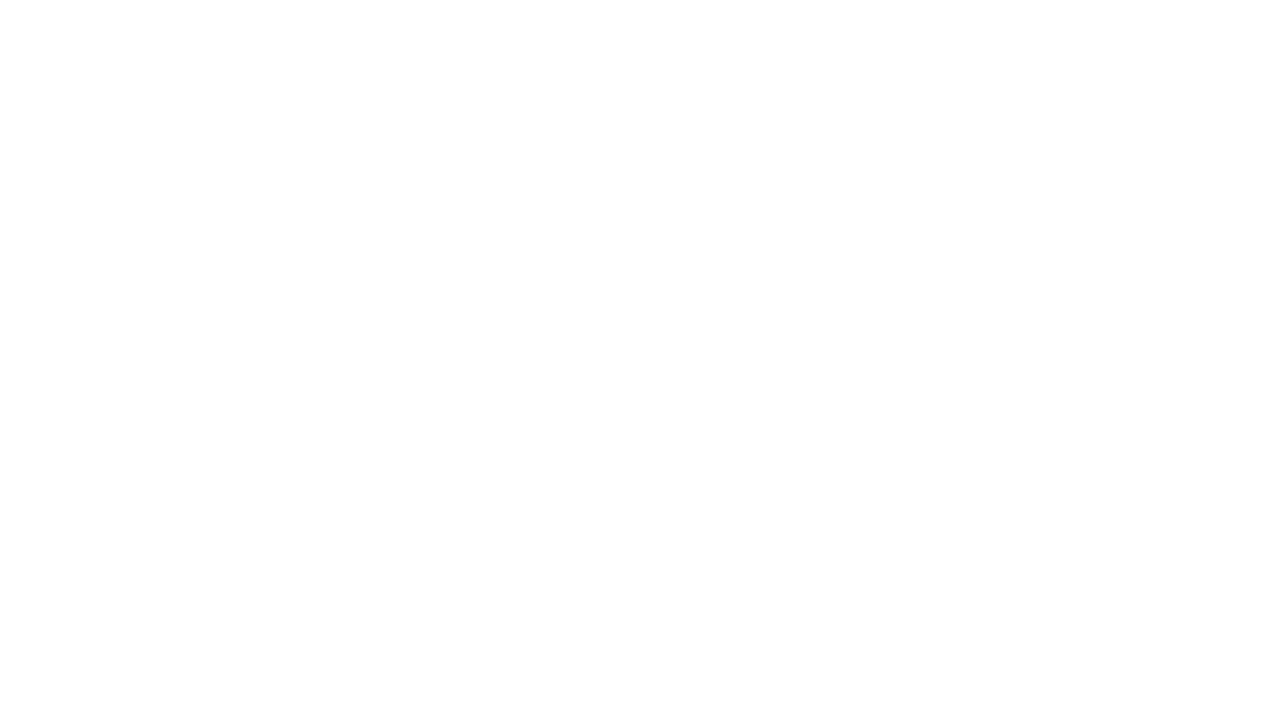
①写真の撮影者:和崎聖日
②撮影場所:ウズベキスタン・スルハンダリヨ州
③撮影年月:2017年8月
≪無断転載ご遠慮ください≫
《内容》
中国東北部の大興安嶺からハンガリー平原まで、草原はユーラシア大陸を東西に貫いています。今から2500年以上前には、歴史上最初の遊牧民(スキタイ)が草原地帯に登場しました。
草原地帯の北と南には定住民の世界がありましたが、ユーラシアの人々の歴史や文化において、遊牧民と定住民の交流は大きな意味を持っていました。発表前半では、これらのことを大まかに見てみましょう。(今村栄一)
発表後半では具体的な例として、現在のウズベキスタンで、みずからの部族の叙事詩などを語り伝えているバフシという人たちとその活動を取り上げます。
1991年のソ連解体によって独立したウズベキスタンは、遊牧民と定住民の交流が大変に活発であった地域を国土として多分に含む国家の1つです。
その意味で、ウズベキスタンはテュルク・モンゴル系の旧遊牧民と、ペルシャ系、ならびにテュルク系の定住民の「文化的なコンタクト・ゾーン」とも形容できます。
ウズベキスタンに残るテュルク・モンゴル系の旧遊牧民はいくつもの部族に分かれていますが、今回は、コングラト部族出身のウズベク人とカラカルパク人を例として、それぞれの民族の構成を説明しつつ、バフシの活動について主に映像をとおして紹介します。(和崎聖日)
《プロフィール》
アルタイ交流舎代表。京都大学文学部西南アジア史専攻卒業。名古屋大学大学院人間情報学研究科博士後期課程満期退学。通算で約14年間、ウズベキスタン、モンゴル、ロシアに滞在。ウズベキスタンでは日本の大学の現地事務所に勤務し、両国間の学術・大学間交流の促進に約8年間携わる。タシケント・キムヨ国際大学客員研究員、立正大学ウズベキスタン学術調査隊委嘱隊員。
アルタイ交流舎ホームページ:https://altai-koryusha.com/

中部大学准教授。主要業績に『中央ユーラシア文化事典』(2023年、丸善出版)や、「ウズベク語におけるクルアーンの解釈と翻訳について」(ハサンハン・ヤフヤー・アブドゥルマジード著・訳稿、2019年、『日本中央アジア学会報』15号、pp. 23-52)、民族誌映画『交霊とイスラーム:バフシの伝えるユーラシアの遺習』(東京ドキュメンタリー映画祭2022 人類学・民俗映像部門コンペティション入選、2022年12月13・22日上映、新宿K's Cinema)などがある。
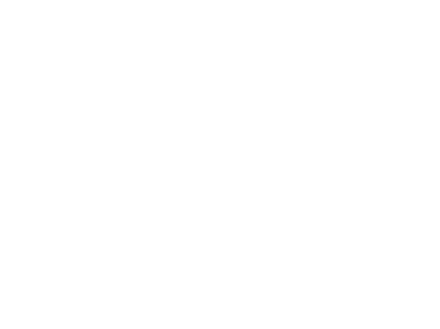
2025年1月15日の「楽平家オンラインサロン」は、「アルタイ交流舎」のお二人のお話しでした。
最初に、「アルタイ交流舎」代表の今村栄一さんより、「歴史の基層から現代の旧遊牧民芸能へ−遊牧世界と定住世界の接触地帯としてのウズベキスタン」というタイトルで発表が行われた。
まず今村さんから「アルタイ交流舎」についての紹介があった。「アルタイ交流舎」は2023年7月に設立され、同年11月に「第1回アルタイ交流舎サロン」を開催、これまで5回のサロンが開催された。またトゥバ楽演奏家・寺田亮平さんによるコンサートや、「ユーラシア民族誌映画を見る会in名古屋」などが開催されてきた。 本題に入り、ユーラシアの東西に広がる草原地帯と、草原で暮らす遊牧民に関する説明があった。中央ユーラシアの草原は、ユーラシア大陸の中緯度帯を、西はハンガリーから東は中国・モンゴルまで帯状に延びており、面積は2億5000万ha(250km2)に及ぶ。その地域に暮らす遊牧民は、1か所に固定した牧場を持たず、年に約2~4回移動し、家畜(五畜、すなわち馬・牛・羊・ヤギ・ラクダ)を飼養する。これら有蹄類の動物の習性に従って人間も移動を繰り返す。 次に、今村さんのご専門である中央ユーラシアの歴史研究に関する3つの立場を、間野英二氏による『中央アジアの歴史』(講談社現代新書、1977年)に基づいて説明された。1つ目は、「東西交渉史、東西交通史」としての研究で、シルクロード研究などがこれに当たる。2つ目は、「中国の西域経営史、西域統治史」としての立場であり、「西域」はほぼ中央ユーラシアをさす。3つ目は、「トルコ民族史」としての研究で、これはもともと草原の遊牧民であったトルコ人が、いかにしてオアシスの定住民となったか、といった問題を扱っている。特に3つ目の「トルコ民族史」の研究者であった間野氏は、中央ユーラシアの住民にとって、東西の交渉よりもむしろ主に北側に居住する遊牧民と南側に居住する定住民の戦争、外交、交易といった「南北」問題の方が重要であったことを指摘した。
続いて、中部大学の和崎聖日さんによる発表「歴史の基層から現代の旧遊牧民芸能へ:遊牧世界と定住世界の接触地帯としてのウズベキスタン」に入った。
まず、本発表の目的は、ウズベキスタン(中央ユーラシア南部)における旧遊牧民芸能の実態と、諸集団の混交の様相を紹介することであり、また同じ「ユーラシア」に位置する日本との関係にも言及することについて説明された。
次に、旧遊牧民芸能とは何かに関する説明が行われた。現代ウズベキスタンでの伝統的な芸能は、定住民(otloq)系と遊牧民(koʻchimanchi)系の2つの類型に区分できる。後者の遊牧民は歴史的に文字を持たず、集団の記憶を詩にして口頭伝承を行ってきた。現在のウズベキスタンでは、遊牧生活を営む集団は皆無だとされるが、自らの帰属意識をかつての遊牧部族に置く人びとも少なからず存在する。このことから、本報告では、彼ら/彼女のことを「旧遊牧民」と呼ぶと定義がなされた。なお、ウズベキスタンが「定住民中心の人口構成」の国家であることも指摘された。
本報告では、旧遊牧民芸能の担い手として「バフシ(baxshi)」と取り上げられた。「バフシ」は都市部を除いて原則的に旧遊牧民地域に存在し、定住民地域には存在しない。また「バフシ」は、①霊媒(女性であることが多い)、②口承文芸・叙事詩の語り手(男性であることが多い)の2種類に分けられる。本報告では、2017年に「ユネスコ無形文化遺産」にも認定された②が対象とされた。バフシ研究の第一人者である坂井弘紀氏(和光大学表現学部)の研究に基づき、「バフシ」の語源には諸説あるが、漢語「博士」であるとする説が有力であると説明された。
また、発表の趣旨を理解するための前提として、以下の2点に関する説明が行われた。
1点目は、中央アジア南部の遊牧民と定住民の関係における、言語面の「テュルク化」の傾向である。北部のキプチャク草原を中心に暮らした遊牧民(テュルク・モンゴル系)の一部は、6〜20世紀の1400年間に、天災や戦争、通商、軍事同盟の締結などを理由に、部族単位で南部のオアシス農耕地帯に移動、定着した。彼らは、ペルシア系定住民の周囲に居住し、遊牧民による略奪から定住民を護衛する役割を果たした。その結果、遊牧民と定住民の接触と融合が起こり、ペルシア系の言語を話す定住民の間にもテュルク語が普及するようになった。
2点目は、中央アジア全体のイスラーム化についてである。8世紀のアラブ人による征服が契機となり、南部(定住民地域)は8~9世紀にイスラーム化が始まった。その結果、旧来の宗教(シャマニズム・ゾロアスター教・仏教等)が駆逐され、中央アジア南部はイスラーム文明の世界的な中心地の1つになっていく。一方、北部(遊牧民地域)は9~19世紀にイスラーム化が進んだが、イスラーム改宗は遅かった。そのため、今日においても、この地域ではシャマニズム的要素が社会慣行に色濃く残る一方、イスラーム文明は相対的に弱い。
このような歴史的経緯により、近代以前の地域住民の帰属意識としては、第1に「宗教」、第2に「定住民/遊牧民」の区分が重要であり、「民族」概念は存在しなかった。現在の「ウズベク人」や「タジク人」等の民族が創出されたのは、1924年に共産党主導で民族・共和国の境界が画定され、現代中央アジア諸国の原型が誕生してさいのことである。その結果、歴史上初めて民族を単位とする近代的な国民国家が創出された。
ウズベキスタンの主要民族は、2021年の統計によれば、テュルク系のウズベク人が約84%と最多を占め、ペルシア系のタジク人は約5%、スラヴ系のロシア人が約2%、テュルク系のカラカルパク人が約2%など、となっている。
ただし、同じ「ウズベク人」の中でも、定住民と旧遊牧民に分けられる。両者の区分の基準となっているものの1つは、帰属意識である。定住民は、「サマルカンド人」といったように場所に帰属意識を持ち、旧遊牧民は、父方の血縁集団である部族(ulugʻ)への帰属意識を持つという点で異なる。また両者で顔立ちもやや異なるが、旧遊牧民系ウズベク人の顔立ちにはグラデーションがあり、区分の基準にならないこともある。
また旧遊牧民系ウズベク人は、①13世紀のモンゴル侵攻以前にこの地に移住し、定住民と交わらず半遊牧生活を送るテュルク系諸部族と、②15世紀にこの地に侵攻し、20世紀初頭に定住生活に移行したテュルク系諸部族、に分かれる。②の中の1つである「ウズベク諸部族」は92部族から構成されるが、本報告で取り上げるコングラト部族はこのウズベク諸部族に含まれる。 コングラト部族は、日本ではモンゴル部族の姻族としてより有名だが、その一部が歴史のさまざまな段階で、現在のウズベキスタン国内のスルハンダリヤヨ州とホラズム州、サマルカンド州、カラカルパクスタン自治共和国などに相当する地域にも移動、定着し、イスラームに改宗した。 上記の説明の後、①スルハンダリヨ州における男性バフシの喉歌を使った叙事詩、②ホラズム州における男性バフシの喉歌を使わない叙事詩、③カラカルパクスタン自治共和国の女性バフシによる叙事詩、の3つの語りの映像が上映された。 最後に、ウズベキスタンでは、北方系の日本人と、ウズベク諸部族に含まれるアルチン(Olchin)部族は遺伝子の塩基配列が一致するという学説などを基に、その真偽は別として、日本人との関係が議論されている現状も紹介された。
その後、質疑応答に入り、以下のようなやり取りが行われた。
Q;バフシはどのように後継者を養成しているのか?
A:伝統的には師匠に弟子入りし、師匠を模倣して学ぶ。近年ではユネスコ無形文化遺産に認定され、ウズベキスタン政府もバフシの伝統芸能を売り出していることから、養成学校も設けられ、教員から学ぶというスタイルも見られる。叙事詩は旧ソ連時代に文字化され、詩集として出版されたものもあり、それらを使用しながら学校で教育が行われている。
Q: 原則、バフシは男性とのことだが、最後の映像における女性のバフシは珍しいのか?
A: 女性のバフシは珍しい。ただ、学校での教育制度ができたことにより、今後は女性のバフシも増えるかもしれない。
Q: バフシの叙事詩に「斜めの眉毛の女性」という歌詞があったが、これは美しい女性の枕詞か?
A: そのとおりである。イスラーム世界では、新月は美の象徴であり、そうしたイスラーム的な価値観が歌詞に反映されているのかもしれない。
Q: バフシは叙事詩を聴いて憶えるため、人によって、また時によって変化するのではないかと思うが、ストーリーの内容も変わるのか?
A: ソ連時代にはイスラーム的な歌詞が削除されて宗教色が抑えられ、民族的な内容にすり替えられた。
Q: 英雄叙事詩の和訳を解釈する際に、日本語の感覚では少し理解しにくい内容や言い回しが多いが、ネイティブの方が聞くと、すんなり理解できる感覚の言葉なのか。
A: 外国人にとってはすんなり理解するのが難しいが、ネイティブでも一般人にとっては聞き取るのが難しい。
Q: ウズベキスタンはソ連の治世下にあったが、その文化的な圧迫などの影響はなかったのか?
A: 上述したようなイスラーム的な歌詞が削除された他、バフシによる社会風刺、とりわけ政治批判を行うことが少なからずあり、政府にとっては原則的にアジテーターとして要警戒の存在であった。
(記事執筆:小島敬祐)
<無断転載ご遠慮ください>
