『楽平家オンラインサロン』
映画で辿る文様と平和
文様〜文字
2024年11月13日(水)
20:00〜
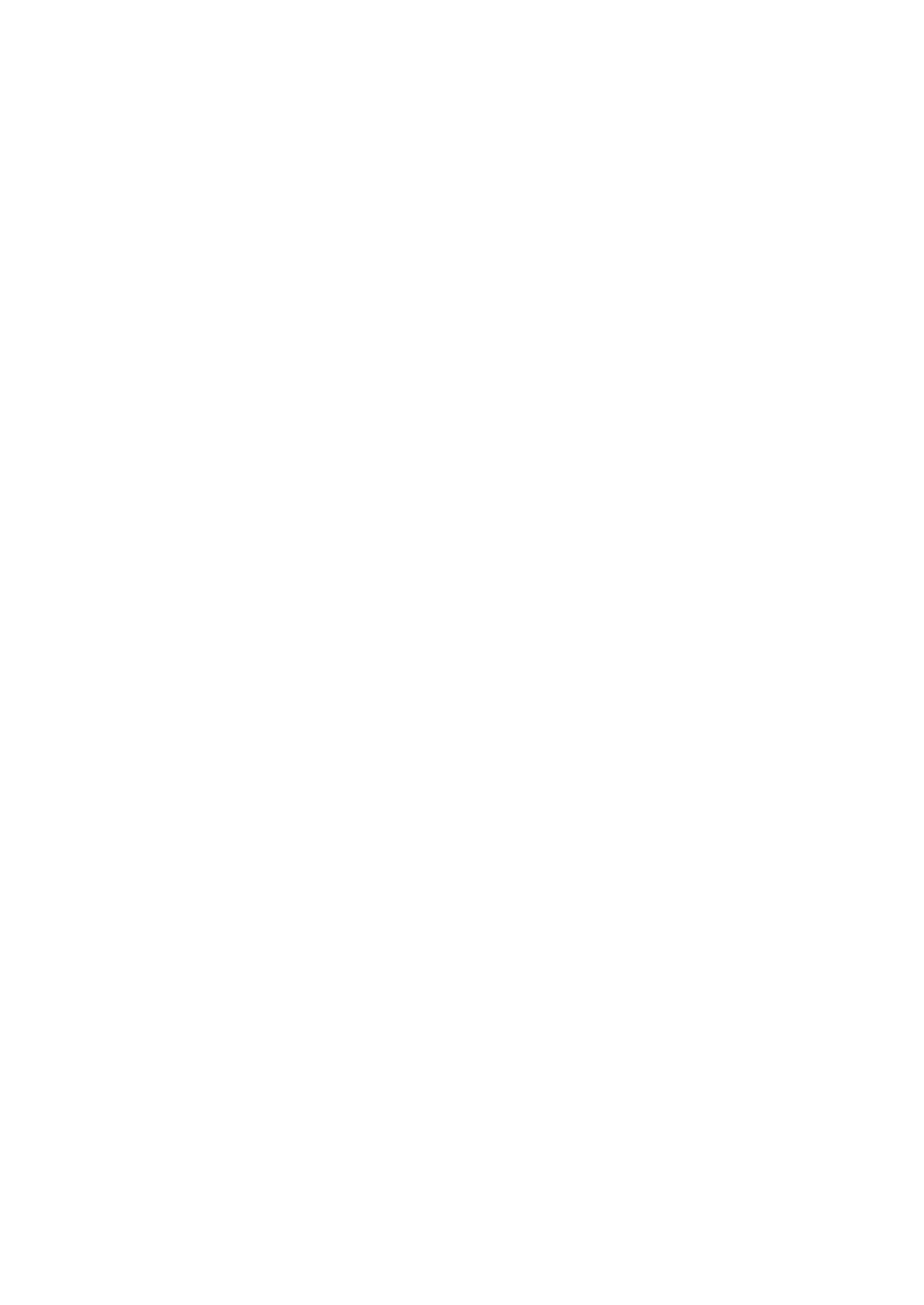
≪無断転載ご遠慮ください≫
話の内容とプロフィール
《内容》
ドキュメンタリー映画「フィシスの波文」は2024年4月から劇場公開し、国年、海外で上映が続いています。文様は最古のメディアであり、人類の普遍のイメージを伝えています。タイトル考案は、人類学者の中沢新一さん。
『フィシス』に込められた意味とは。
文様が辿ってきた道から、人類の未来について考えていきます。
《ストーリー》
遠く、深く、文様に導かれた旅。
京都に400年受け継がれる唐紙文様を起点に、太古から文様にかたどられたフィシス(あるがままの自然)を辿る。 時空を超えて、そのあわいに見えてくるものはー
京都の唐紙工房「唐長」は、和紙に文様を手摺りする唐紙を400年間継承してきた。その手仕事の現場から、本作は始まる。
植物文、雲や星を表す天象文、渦巻きや波文などが刻まれた江戸時代の板木に、泥絵具や雲母を載せ、和紙に文様を写していく。その反復によって生み出される唐紙の、息をのむような美しさ。あるがままの自然のかたち、動き、リズム、色合い。文様と、自然の「かたち」や「気配」をカメラは丁寧に追っていく。
葵祭や祇園祭、寺社や茶事の空間に息づく文様。1万年余り前のイタリアの線刻画や古代ローマの聖堂を飾るモザイク。北海道のアイヌの暮らしに受け継がれている文様。時空を超えて旅は繋がっていく。
エルメスのアーティスティック・ディレクター、デザイナーの皆川明(ミナ ペルホネン)、美術家の戸村浩は、自然からのインスピレーションと、自らの創作について真摯に語る。密やかに行われるアイヌの儀式や山の神への祈りは、人と自然と文様との関係性を、より鮮明に浮きあがらせる。
小さな京都の工房から多層的に拡がる文様を巡る旅の記録が、私たちが忘れてしまった大切な感覚、全人類の古層とのつながりを思い出させてくれる。
『フィシスの波文』プロデューサー インテリア・プロダクトデザイナー
古代から現代まで世界各国の「文様」をテーマにしたドキュメンタリー映画『フィシスの波文』を企画・製作・プロデュース・配給。インテリア・プロダクトデザイナーとしても活動する。SASSO CO., LTD.代表。
公式HP https://physis-movie.com
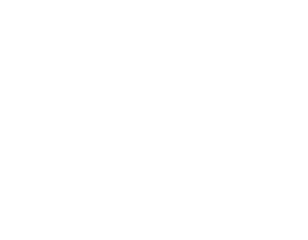
2024年11月13日開催の「楽平家オンラインサロン」は、河合早苗さんによる「映画『フィシスの波文』を巡って―世界が一つになる文様―」のお話しでした。
お話しの冒頭に映画「フィシスの波文」(予告編)を見せていただいた。版木の上にふわっとのせた白い紙を両手で静かに、板木に彫られた文様を確実に写し取る音が「シュシュ」と聞こえる。京都の唐紙屋「唐長」の仕事場風景だ。
この映画は唐長の板木を基にした文様が京都の有数のお寺などで襖などの意匠としていまも活躍していることをきれいな映像で描いている。同時に、文様のありようを世界に探り新鮮な視点で物語っている。
ケルト、唐長、アイヌを結ぶ
この映画の企画・制作のプロデューサーである河合早苗さんが話を始める。かつて、イタリア・ミラノの建築事務所でデザイナーとして働いていた時、文様のパターンをずっと見て参考にしていた。イタリアに在住している時にはスコットランドの北西の島を訪ね、ケルト文様に初めて出合った。その後、帰国して、1991年、「唐長」を京都・修学院にインテリアの仕事で訪れる。唐長には文様を彫りこんだ650もの板木があり、400年変わらない手摺りで唐紙をつくっていた。
「文様に何か秘密があるのでは」と興味を持ったのは唐長を知ってからだが、思い起こせば大学の時にアイヌ文化を学んだこともつながってきた。
美術大学2年の時、夏休みに北海道・二風谷(道央・平取町)の牧場で1カ月間、牧草の刈り入れ、豚小屋の掃除などのアルバイトを経験。滞在中、アルバイト先の近くに住んでいたアイヌ文化研究者、萱野(かやの)茂さんが綿々とアイヌ文化を説明してくれた。話の中でアイヌには文字がなかったことを知り「衝撃的だった」。アイヌの文様が描かれた衣装も見た。
こうした文様を巡る北海道と京都・唐長のことが河合さんのなかで「踊りと歌、そして文様が文化を伝えてきたのでは」という考えが浮かぶ。映画では雪の中でアイヌの2人の男性が文様をあしらった衣装で舞う様子(歌い手は女性)を撮影した場面が登場する。
この映画の題名「フィシスの波紋」の「フィシス(Physis)の意味は古代ギリシャ語で生まれ、育ち、死に、再生するという生きものの変化を自然ととらえる意味です。これは日本の自然観である『自然・じねん』に近い」という。波文は平安時代に表記されたもので、のちに波紋が使われるようになった。カタチ(文様)であり、動態(波動)でもある。「文」には兆しの意味もあり、「じねんの動き」を表す題名とした。映画の題名に迷った河合さんが旧知の文化人類学者中沢新一さんに相談して題名を決めた。
文様の共通性
日本や世界各地で河合さんが発見した文様の文様との間には似たようなものがあることに気づく。その一つが「三つ巴」文様。河合さんのプレゼンテーションであげたのが図1だ。
左下はケルト文様の一部で、円形のなかに円形があり、その中に三つ巴の文様が記されていく。右上が学生時代の時、見たアイヌ衣装の三つ巴文様。「生命感のあるものだ」。
河合さんはこう考える。「ケルトとアイヌの文様は(デザインが)近い。ユーラシア大陸の西端と東端で同じよう自然観、人生観を持ったのではないだろうか」と想像する。「(それぞれの文様たちから)受ける印象が近い」という思いを大事にし、その思いを映画づくりのきっかけとしてつなげていった。
図1右下が京都・祇園祭の山車に掲げられた提灯にやはり「三つ巴」文。祇園祭を行う八坂神社のご神紋(しんもん)は「三つ巴」と「うり」だ。

「渦巻」文様は続く
「渦巻」はほかにもあった。イタリア・カモニカ渓谷(ミラノから北東116Km)の岩絵群のなかにある「4つのぐるぐる文様」が岩の上に刻み込まれたのが4000年前。世界中に同じような文様が存在する。マルタ島の寺院遺跡にもこの4つのぐるぐる文様にそっくりなものがあった(図3)。
官休庵(図2左下)は表、裏と並ぶ千利休から続くお茶の家元。官休庵の水屋の襖にはあざやかな白い渦の文様が浮かぶ。唐長(図2中)の細渦は水の動きを表現しているようだ。
角がついたような渦もある。河合さんは「角に何かの意味があるのでは」と問う。


文字の前は文様で表現していたのか
イタリアのカモニカ渓谷の岩に彫られた文様は1万年ほど前から8000年間、続いた、といわれる。それが紀元100年ごろに文様に代わって古代ローマ字がこの岩々に刻まれて登場する。コミュニケーションの表現形態が変わった画期的な時代だ。
文様はいまも生きている。フィシスがいう生きものがいきているように。河合さんは講演で繰り返し言う。「世界に文様のエビデンス(証拠)を探る」と文様の映画化を進めるに当たって、文様の現場に行くことを大事にしてきた。「小さな京都の工房から時空を超えてひろがる」という河合さんの問題意識が本人を動かし世界の「文様」を探し求めた。
5年にわたる映画の撮影で河合さんが聞いた、唐長の11代目千田堅吉さんの一言は文様のすべてを語っている。「自分の思いを入れてはいけない。主役は文様です」。
(写真の著作権はすべて(C)SASSO.CO.,LTD.)
(記事執筆;太田民夫)
<無断転載ご遠慮ください>
